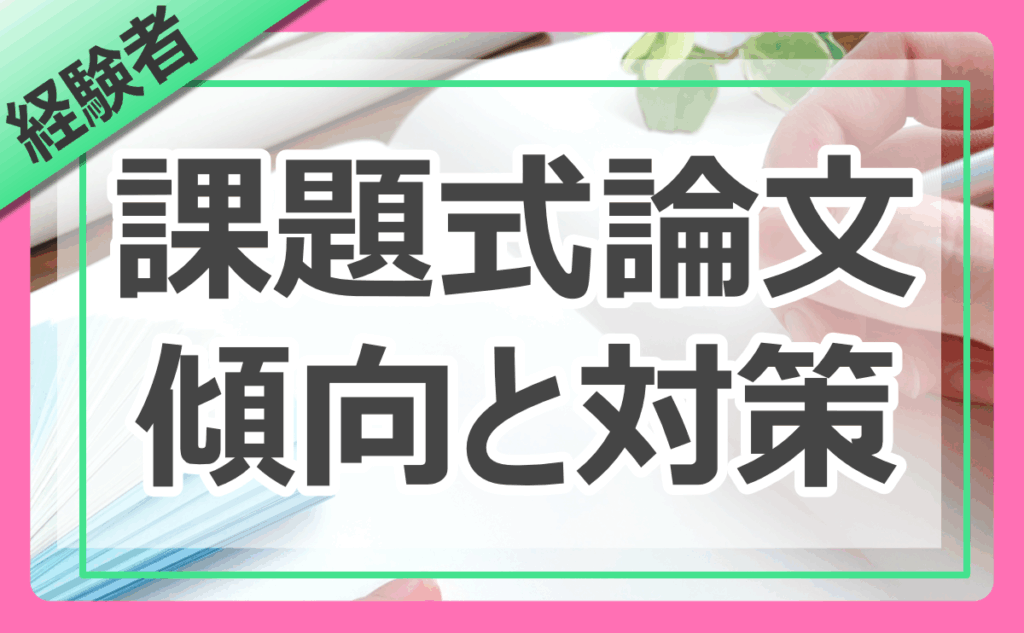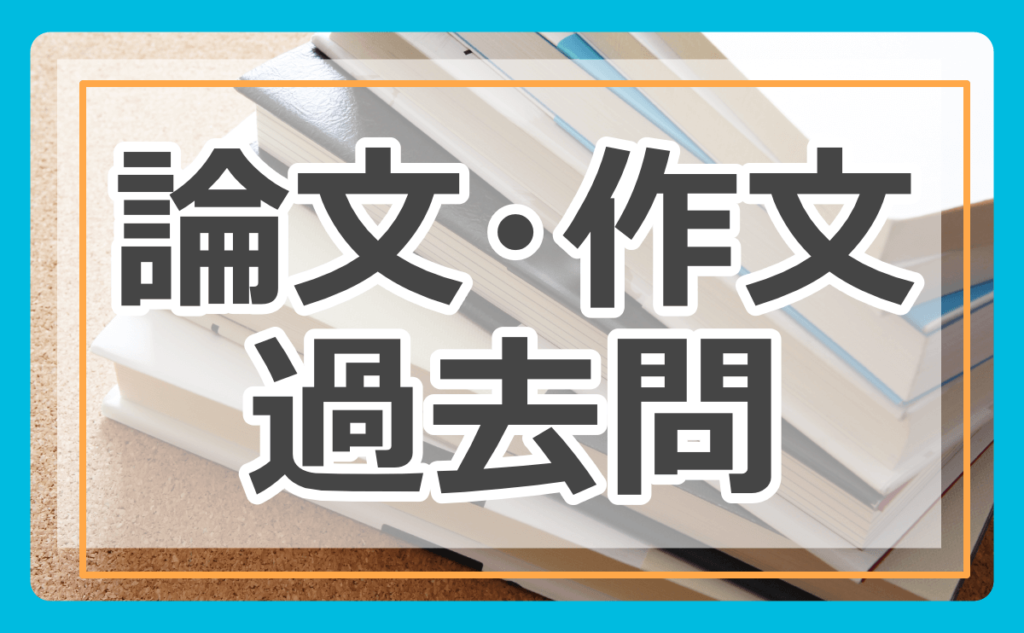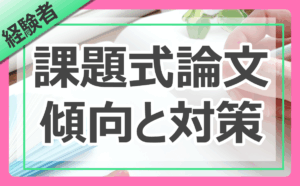【特別区経験者採用】職務経験論文のポイントと失敗例をプロが解説!
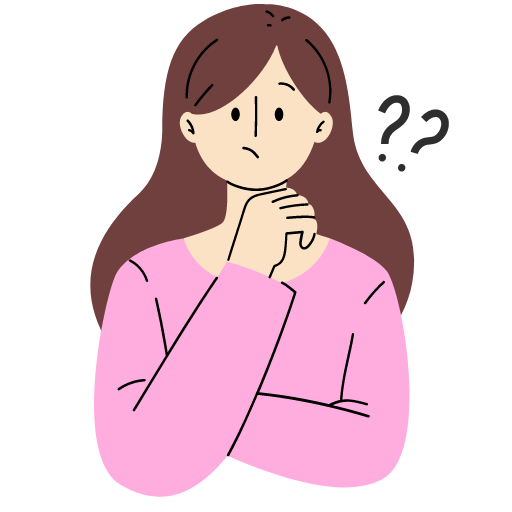
職務経験論文ってどんなことを書けばいいの?
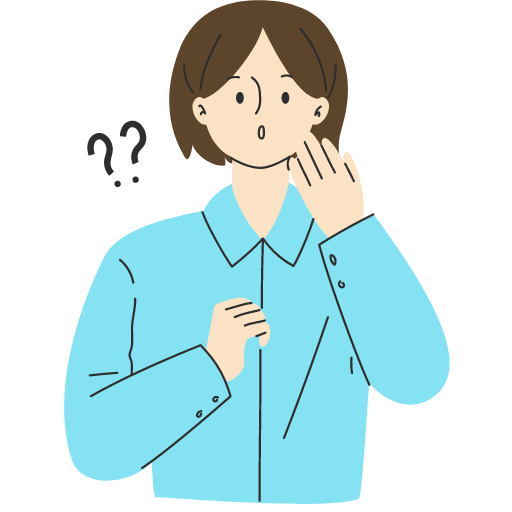
どんなテーマが出てくるのかな?
特別区経験者採用は、民間企業や公的機関での職務経験を活かして特別区を目指す人のための採用試験です。
受験者の年齢層は30〜40代が中心で、社会人としての実務経験が評価される点が特徴です。
特別区の職務経験論文は課題式論文とは異なり、自身の職務経験をもとに記述しなければならない点に難しさがあり、多くの受験生を悩ませています。
そこで本記事は、特別区経験者採用を目指すあなたに下記のポイントを紹介していきます!
この記事で分かること
- 出題傾向
- 構成の立て方・書き方
- 評価ポイント
- よくある失敗例と対策
職務経験論文では、あなたがどのような職務経験を積み、どのような課題に直面し、どのように解決してきたのか、そしてその経験を特別区の行政職としてどう活かしていくのかを、限られた文字数の中で論理的に伝える必要があります。
難しそうだと感じる人も多いですが、課題式論文と比較すると職務経験論文は事前の準備や練習次第ではむしろ高評価を狙いやすいので、ぜひしっかり対策をして臨みたいものです。
コツさえ掴めば誰でも書けるようになります!ぜひ参考にしてくださいね。
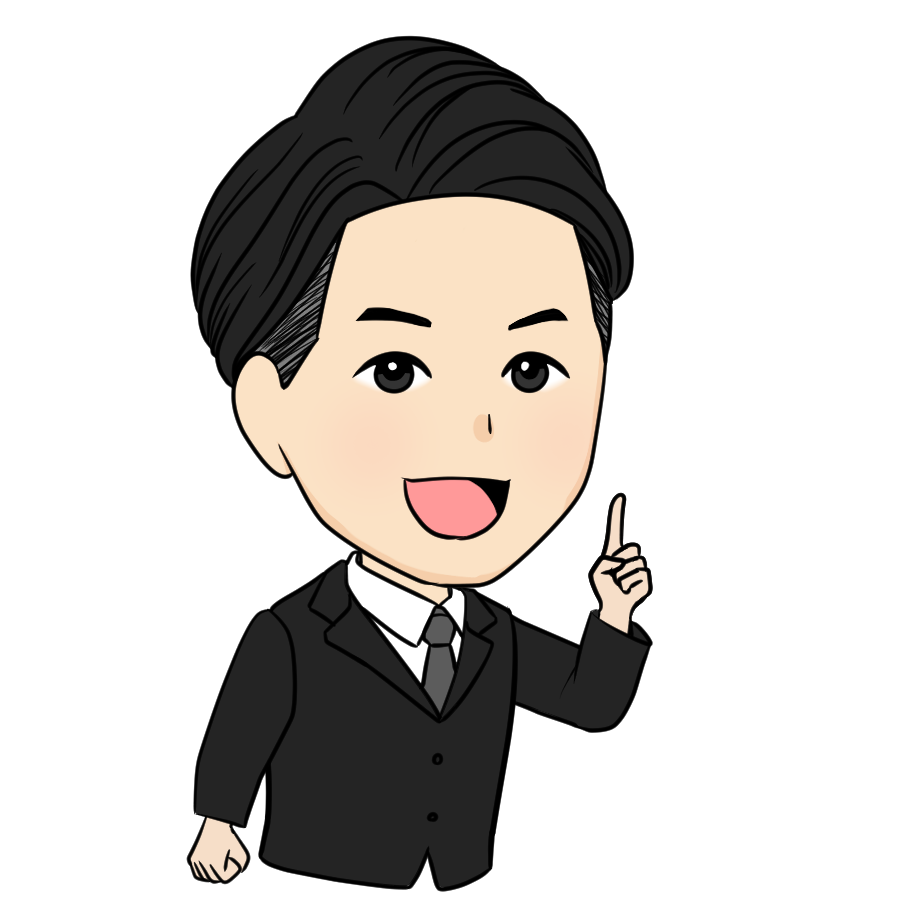
なお、特別区経験者採用の課題式論文のポイントや注意点については、下記の関連記事で解説しているので併せてチェックしてみてください!
関連記事はこちら
職務経験論文とは?
具体的な内容に入る前に、そもそも職務経験論文とは一体どういった試験なのか?基本を解説したいと思います。
まず、職務経験論文とは特別区経験者採用の1次試験で実施される論文試験で、試験時間90分、文字数は1200~1500字です。
論文ですからもちろん文章力も必要ですが、それ以上に「過去の実務経験から行政職に必要な資質が備わっていること」を示すほうが重要です。
行政の視点で物事を捉え、課題に対して主体的かつ論理的に行動してきた経験を、明確に表現できるかどうかが評価の分かれ目と言えます。
そして、職務経験論文で評価される能力としては次のようなものが挙げられます。
求められる能力
- 論理的思考力
- 問題発見力と課題設定力
- 行動力と協働性
- 組織マネジメントの視点
- 行政職への応用力
これらはすべて、これまでの民間での業務においてあなたがどのように考え、行動し、他者と連携して成果を出してきたかを問うものです。
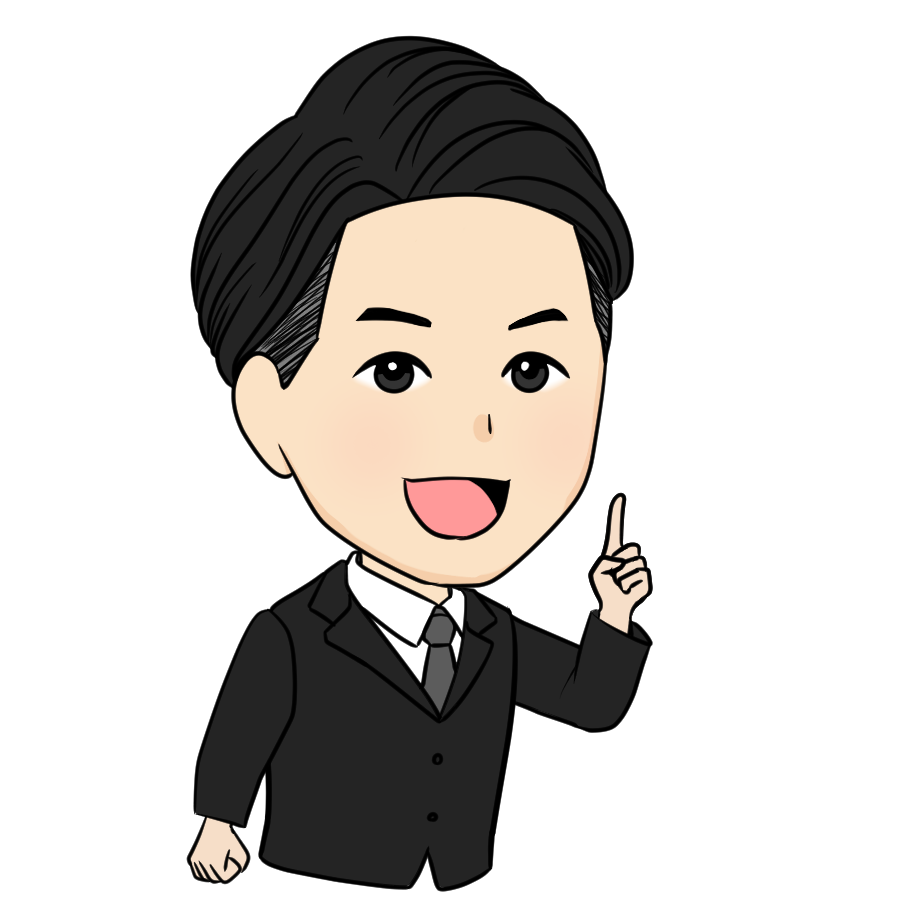
自身の経験を単に「成果」として語るのではなく、「この経験を活かして区民のためにどう貢献できるか」という公的視点を持って述べることを忘れないようにしましょう。
過去問から見る出題傾向
それでは、実際にどのような問題が出題されているのかチェックしていきましょう!
過去問を把握しよう!
3年分の過去問を見ていきます。
【2024年度】
行政におけるコンプライアンスの重要性について、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて採用区分における立場で論じてください。
出典:2024年度 特別区経験者採用試験 職務経験論文問題
【2023年度】
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場での取組について、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて採用区分における立場として論じてください。
出典:2023年度 特別区経験者採用試験 職務経験論文問題
【2022年度】
職場の活性化について、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて採用区分における立場として論じてください。
出典:2022年度 特別区経験者採用試験 職務経験論文問題
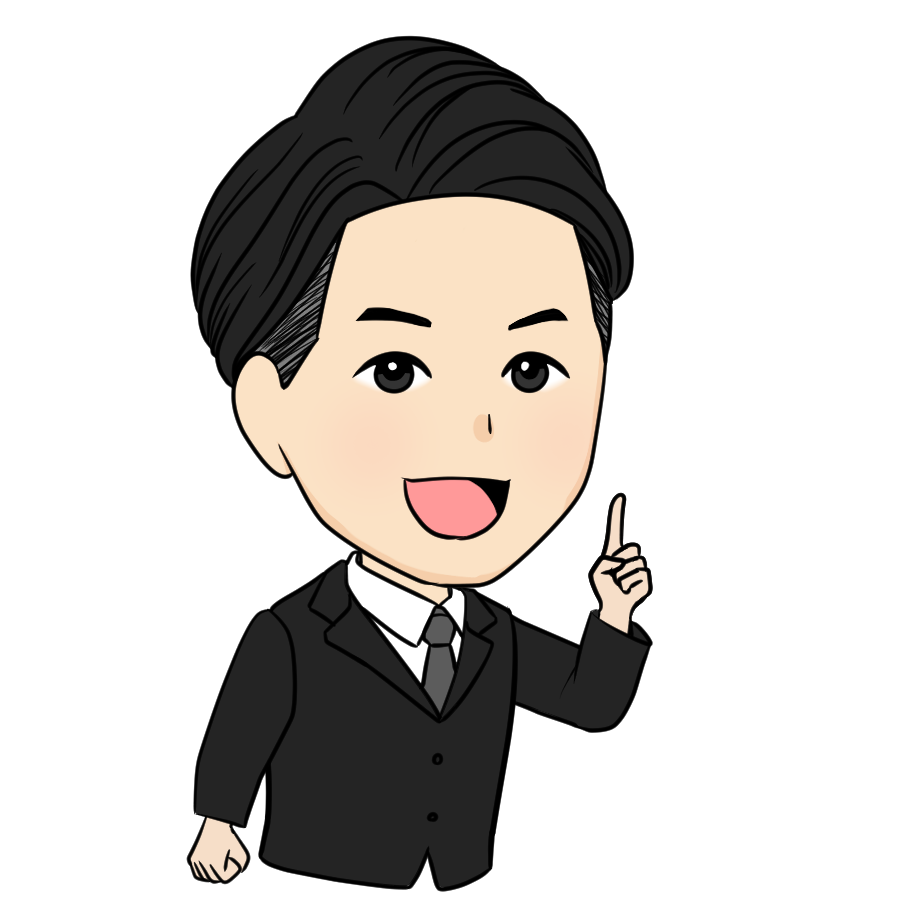
過去問の続きは下記の関連記事からチェックしてみてください!
関連記事はこちら
過去問を見てみると、どの年度も次の3点が書かれていることが確認できます。
問われていること
- 論文のテーマ
- これまでの職務経験を最初に述べること
- テーマについて「職務経験」と「採用区分における立場」をふまえて論じること
過去問を見ると分かるように、❶の論文テーマは毎年変わりますが、❷❸の部分は下記のとおり毎年同じです。
- あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて採用区分における立場として論じてください。
したがって、出題が予想される様々なテーマについてこの形式で書く練習を積んでおくことが、非常に有効な対策となります。
特に職務経歴の部分は試験前にしっかり作り込み、本番ですぐに書けるようにしておくことがポイントです。
そして、出題テーマには「特別区が実際に直面している課題」や「社会問題」が反映されているので、特別区のホームページなどを調べて各区の現状や課題をしっかり把握しておくことが大切です。
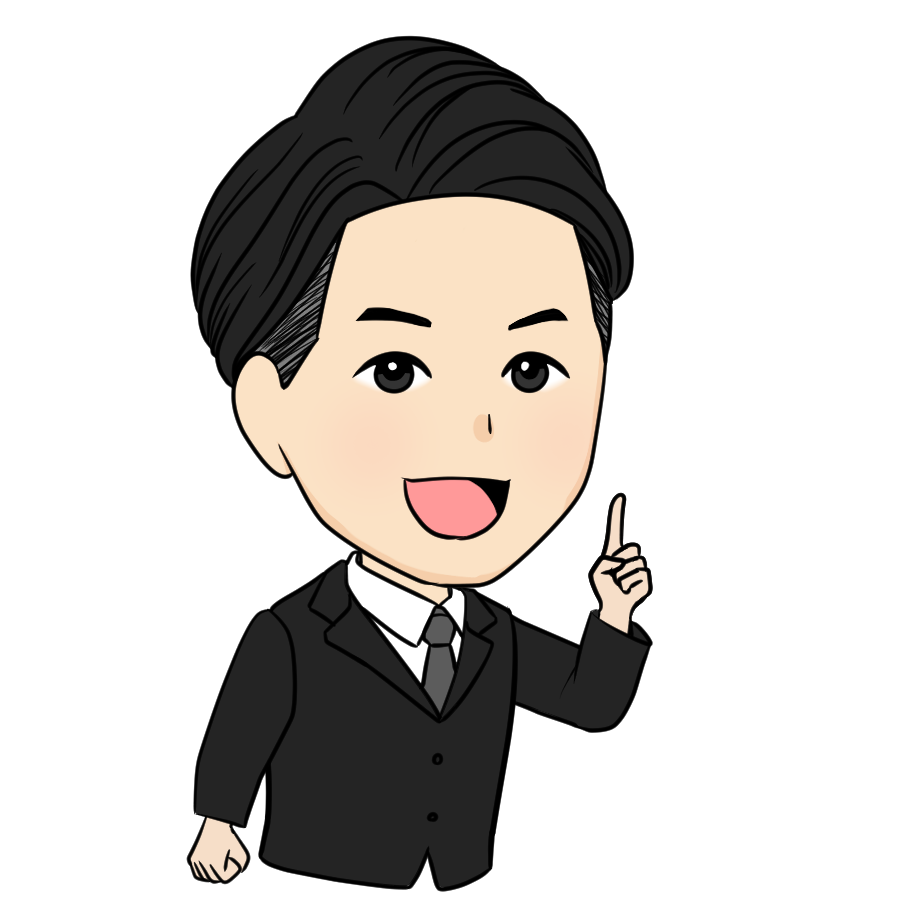
似たようなテーマが数年ごとに出題される傾向があるので、過去問で合格答案が書けるように練習しておきましょう。
なお、「技術職」や「ICT職」では別テーマが出題されており、職務経験のほかに専門知識を踏まえて論じるよう指示されている点が事務職とは異なっています。
しかし、出題テーマは「デジタル技術の活用」「脱炭素化」など、時事問題を押さえていれば対応できる範囲なので、しっかりと対策をしていれば恐れることはありません。
頻出テーマと対応策
特別区の職務経験論文では繰り返し出題されているテーマがあるため、論文対策を進める上ではまずこれらのテーマを優先的に対策していくのがオススメです。
頻出テーマ
- トラブル・リスク対応
- 業務の効率化
- コミュニケーション上の工夫
トラブル・リスク対応においては、業務上のトラブルやリスクに対してどのように対応したかを述べます。
問題発生時の冷静な判断や関係各所との調整、再発防止策などを具体的に記述しましょう。
また、業務の効率化については、業務プロセスの見直しや改善提案など効率化に向けた取組を紹介していくとよいでしょう。
民間企業での経験は即戦力として行政の業務改善に活かせる要素が多いため、具体的な成果を示すと効果的です。
そして、職場内外での円滑なコミュニケーションを図るための工夫や取組は、多様な関係者との連携や調整力について言及できると、行政職員としての資質がアピールしやすいです。
本番で時間を有効に使えるよう、それぞれの頻出テーマに対して自分の経験をどのように活かせるかをあらかじめ考えておくようにしましょう。
論文を書く前の下準備
ここからは、具体的な対策方法について解説していきます。
職務経験を棚おろしする
職務経験論文で記述するエピソードを選ぶには、まず自分の経験を振り返ることが欠かせません。
次の6つのポイントについて、それぞれ可能な限りたくさん書き出してみましょう。
自分の経験を振り返る
- 業務内容:どんな仕事をしていたか
- 課題と背景:どんな問題に直面したか
- 自分の行動 :どんな工夫をし、どのように行動したか
- 成果 :どんな結果が出たか、どんな評価を受けたか
- 学び :その経験から何を得たか
- 行政への応用:経験を行政でどう活かすか
「業務内容」はどのようなテーマが出題されても書くことは同じなので、自分が民間でやってきたことがよく伝わるように練り上げ、100字程度でまとめておくと本番でもそのまま使えます。
また、「課題と背景」以下の部分は与えられたテーマによって変わるので、「このテーマが出たらこのエピソードを使おう」という形でテーマごとにいくつかのパターンを用意しておくのがオススメです。
その際重要なのは、ただ成果をアピールするのではなく、「どう考え、どう行動したか」をできるだけ具体的に書き出すことです。
実際には文字数が限られるため割愛せざるを得ない部分が出てきますが、ひとまず書き出したあとで最も適したエピソードを選び、要点を絞って端的な表現にブラッシュアップしていきましょう。
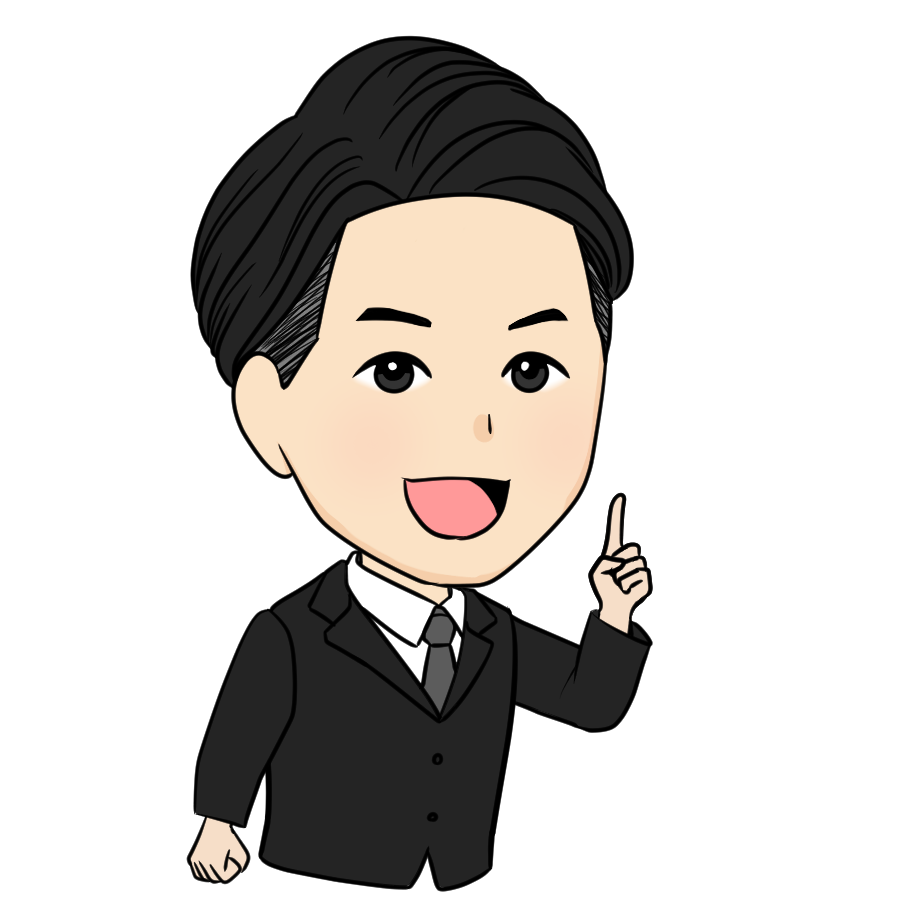
これらの項目について振り返っておくことは、エントリーシートの記入や面接の際にも大いに役立つので、ここは面倒がらずじっくり取り組むようにしてくださいね。
採用区分ごとの視点を忘れない
職務経験論文では「採用区分ごと」の視点も重要です。
特別区では職歴年数により、以下のように採用区分が分かれます。
| 区分 | 主な役割 |
| 1級職(係員級) | 実務の担い手、若手職員 |
| 2級職(主任級) | 中堅職員として業務遂行 |
| 3級職(係長級) | 課や係のマネジメント層 |
職務経験論文では単に経験を語ればよいのではなく、「この区分で働く立場としてどのように行政に貢献できるか」を明確に述べることが求められています。
1級職であれば、クレーム対応で顧客満足度を向上させた経験やデータ管理業務でミスを減らすための工夫を行った経験など、自分が実務を行う上で取り組んだ創意工夫をアピールします。
2級職では、業務マニュアルを見直して業務効率化を図った経験、後輩指導やOJTでチーム力を底上げした経験など、1級職よりも広い視野での貢献や後輩への対応などを書くことになります。
そして3級職になると、部署間の調整を通じて業務を円滑に進めた経験やプロジェクトリーダーとして成果を上げた経験など、組織マネジメントや部下育成、部門間調整といった視点が求められます。
そのため、経験の棚おろしの段階で、採用区分にふさわしい視点でのエピソードかどうかをチェックする必要があります。
採用区分にマッチしない経験を書いてしまうと、どんなに素晴らしい経験でも評価されない恐れがありますので、十分注意しましょう。
論文の構成と書き方のポイント
下準備ができたら、いよいよ実際に論文を書く段階に入ります。
ここでは、職務経験論文の基本構成とポイントについて解説していきます。
基本の4段階構成
職務経験論文は、次の「4段階の構成」を頭に入れておくと書き進めやすくなります。
職務経験論文の4段階構成
- 業務内容の概要
- 課題と行動:課題発見→工夫・行動→周囲との連携
- 結果と学び:成果、自己の成長
- 行政への応用:行政職への展望、意欲
この構成に当てはめることで文章が論理的に整理されたものになり、読み手にとっても読みやすくなります。
論文では独自性を出そうとするのではなく、このような「型」を意識することが最も効率的かつ効果的な対策方法といえます。
業務内容の概要
業務内容の概要では、自分がどのような業務に従事してきたかを説明します。
この部分では、業種や部署の概要、そして担当した業務内容を簡潔に記述するようにしましょう。
重要なのは「行政職でもイメージできる言葉」に可能な限り置き換えることです。
例えば、営業職での「顧客対応」を行政職で言うならば「住民対応」や「区民サービス」に置き換えるなど、民間企業での経験をそのまま書くのではなく行政の文脈で説明できるように工夫が必要です。
課題と行動
次に、自分が直面した具体的な課題について述べ、どのようにそれを解決に導いたかを説明します。
問題をどう発見し、どう考え、どのような行動を取ったのかを順を追って記述していきましょう。
例えば、あるIT企業で「システム遅延が慢性化していた」という問題であれば、どのように情報を収集し、原因を特定して改善策を提案したかを具体的に説明します。
ここでは単独での行動ではなく、他部門とどのように協力して問題を解決したのかを強調するとよいでしょう。
結果と学び
行動の結果は、成功でなくても構いません。
大切なのは、その結果からどのような学びを得たのか、自己成長にどうつながったのかを明確にすることです。
行政職では「問題発見力」「業務改善力」「調整力」といったスキルが重要であるため、これらの点に関連する学びを具体的に述べるとよいでしょう。
例えば、プロジェクトの成功を通じて「調整力が向上した」「問題解決のアプローチが明確になった」など、行政職においても活かせるスキルを学んだことをアピールしましょう。
行政への応用
最後に、その経験がどのように特別区行政で活かせるのか、合格できたら特別区にどのように貢献したいのかを述べます。
この部分では、現状を踏まえた上で未来志向の姿勢を見せることが高評価につながるでしょう。
自分の経験が特別区行政でどのように活かせるのかを考え、その意欲を示すことが重要です。
書き方のポイント
次に、職務経験論文の書き方のポイントを整理しておきましょう。
職務経験論文の書き方のポイント
- 主語と述語が正しく対応しているか
- 一文が長すぎないか(目安:40字程度)
- 抽象語の羅列ではなく具体的行動を書いているか
- 定量的成果(数値、評価)を入れて説得力を増しているか
- 行政職員としての視点を意識して書いているか
文章の書き方自体は通常の論文と同様ですが、具体的に書くこと、定量的成果を入れること、行政職員としての視点で書くことに注意しましょう。
練習の時からこれらのポイントを頭に置いて、書いたり読み直したりすることが大切です。
【絶対回避】よくある失敗例と対策
次に、職務経験論文を書く際に失敗しがちなポイントとその対策方法を見ていきましょう。
受験生が犯しがちなミスには主に下記の3つがあります。
職務経験論文のよくある失敗3選
- 「なぜできたのか」が見えない
- 「自分視点」に終始し、周囲との関係性が書かれていない
- 抽象的な表現が多く、読み手に伝わらない
最も多いのが、成果だけを誇張し「なぜできたのか」が見えない答案です。
職務経験論文においては成果だけを書くのではなく、どのような課題があったのか、それに対してどのような工夫をしたのかを詳細に述べることが重要です。
結果をアピールすることは大切ですが、その背後にあるプロセスや思考過程を記述することで、面接官に納得感を与えることができます。
また、評価の低い論文には周囲との関係性が書かれていないものも多いです。
行政職ではチームワークや他部署との連携が求められるため、自分一人で成果を上げたのではなく、周囲との協働・調整があってこその成果であることを強調することがポイントとなります。
そして、抽象的な表現が多い論文は読み手に伝わりにくいため、具体的なエピソードを交えて「誰が」「何を」「どうしたのか」を詳細に記述することが求められます。
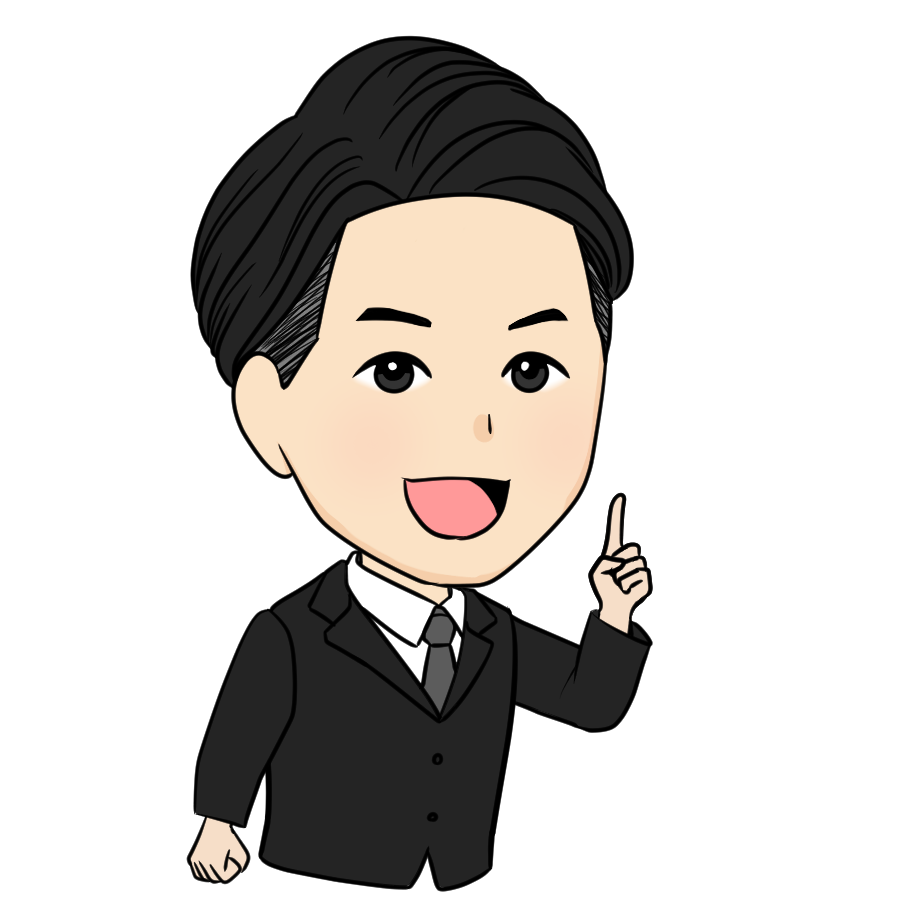
「5W1H」を意識して、出来事を具体的に描写することで読み手に伝わるように工夫しましょう!
このような失敗を起こさないために、受験生の皆さんには下記のポイントをおさえておいてほしいと思います。
失敗を起こさないための対策方法
- 第三者に読んでもらう(添削やフィードバック)
- 「行政職で同じ状況ならどうするか?」と自問してみる
- 業界用語を行政向け表現に変換する
論文というのは第三者に見てもらうことが必須の科目であり、自分では気づかない表現の曖昧さや不足している部分を指摘してもらうことが必要です。
自分以外の人からの客観的な意見を聞くことでより完成度の高い文章に仕上がるため、周囲の人や予備校講師などに読んでもらい、気づいた点をフィードバックしてもらいましょう。
また、記述にあたっては「民間企業の経験を行政にどう活かせるか」という視点を忘れてはなりません。
自分の経験を行政職に応用する方法を考え、その視点を文章に反映させることを常に意識しましょう。
そして、業界用語は専門的すぎて伝わりづらい場合があるため、行政職でも通じる表現に置き換えることが求められます。
これを練習の時から意識することで、より行政職に適した内容の論文が書けるようになります。
まとめ
今回は、特別区の職務経験論文について、出題傾向や構成の立て方、書き方、評価ポイント、頻出テーマへの対処法などについてお伝えしました。
職務経験論文はあなたがこれまで何をしてきたかだけではなく、「その経験をもとに特別区でどう貢献できるか」を語るための文章です。
つまり、過去と未来をつなぐ「ストーリー」を描く作業になるので、自分の経験を行政の文脈に変換し、読み手に「一緒に働きたい」と思わせる内容に仕上げたいものです。
そのためには時間をかけて自己分析を行い、第三者の意見も取り入れながら何度も書いて推敲を重ねましょう。
練習を繰り返せば必ずブラッシュアップされていくので、苦手意識がある人も諦めることなく、あなたの経験が持つ価値を職務経験論文で伝えていきましょう。
健闘をお祈りしています!
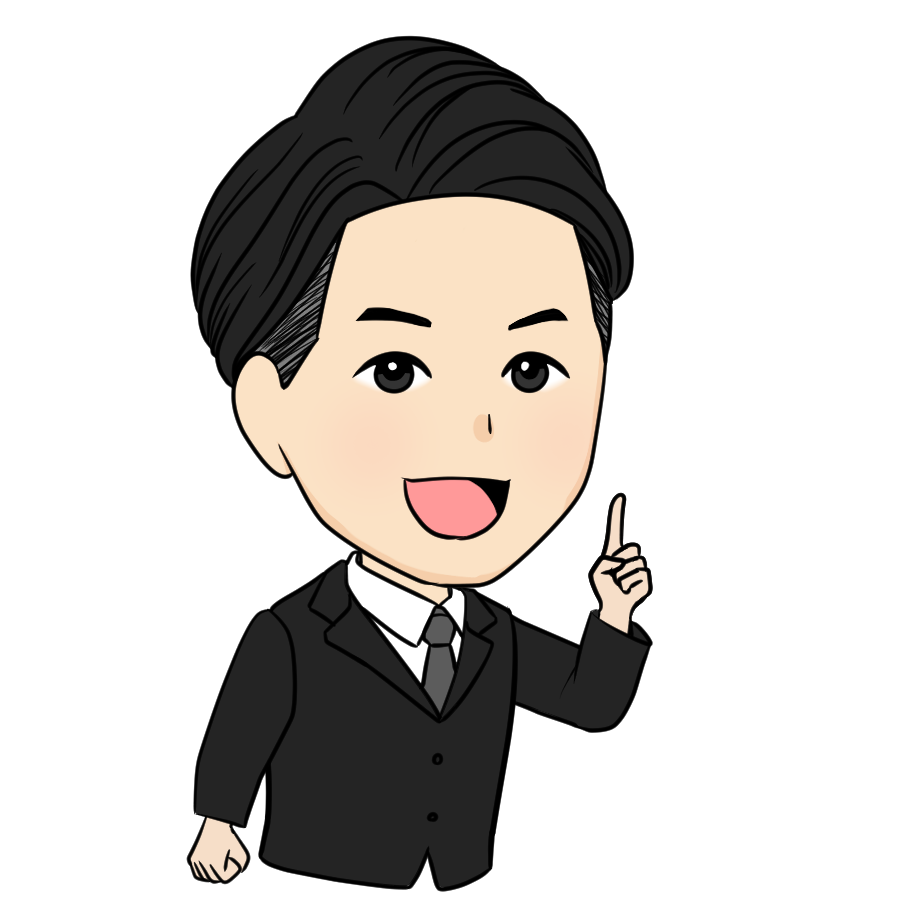
特別区経験者採用の課題式論文のポイントや注意点については、下記の関連記事で解説しているので併せてチェックしてみてください!
関連記事はこちら
予備校概要

- プロコネクトは「特別区対策に完全特化」した予備校です。コンセプトは「日本で一番特別区対策に強い予備校」&「必要な指導を、必要なときに必要なだけ」。個別ニーズに応じた指導を提供し、受験生の合格力を一気に高めます。特別区を目指すなら、専門予備校プロコネクト!
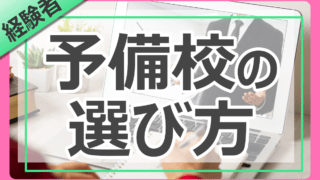 特別区経験者採用2025年12月22日【特別区経験者採用】社会人の予備校選び!おすすめの選び方とスクールは?
特別区経験者採用2025年12月22日【特別区経験者採用】社会人の予備校選び!おすすめの選び方とスクールは?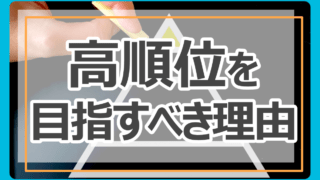 特別区全般2025年12月22日【特別区】高順位を目指すべき理由!低い順位は採用漏れ…?
特別区全般2025年12月22日【特別区】高順位を目指すべき理由!低い順位は採用漏れ…?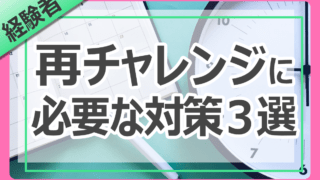 特別区経験者採用2025年12月22日【特別区経験者採用】再受験組が合格するための対策3選!
特別区経験者採用2025年12月22日【特別区経験者採用】再受験組が合格するための対策3選!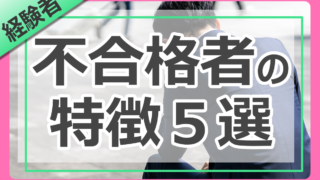 特別区経験者採用2025年12月22日【特別区経験者採用】不合格になる人の特徴5選!
特別区経験者採用2025年12月22日【特別区経験者採用】不合格になる人の特徴5選!