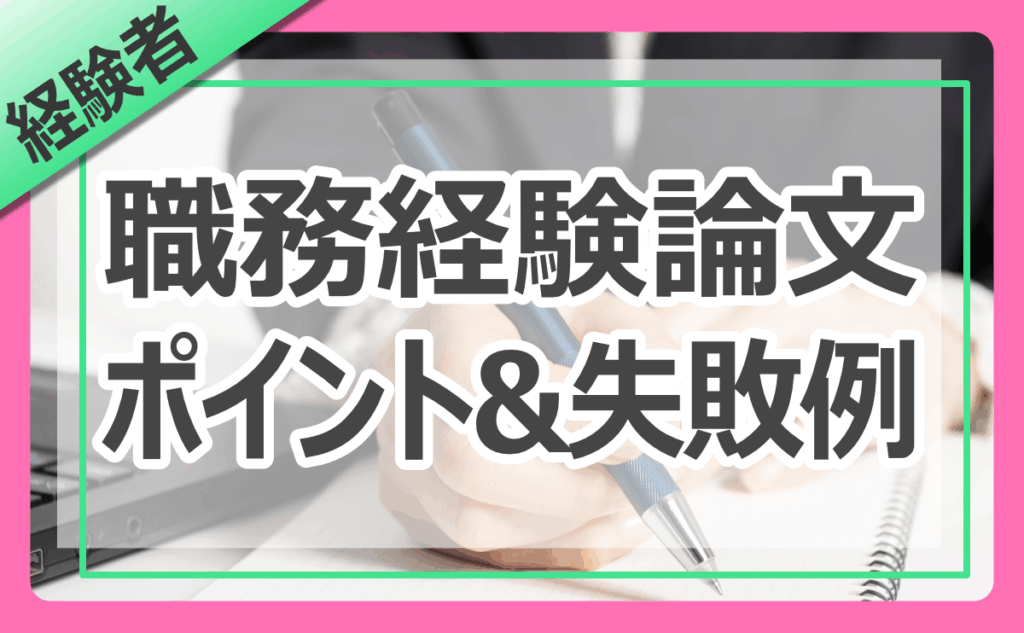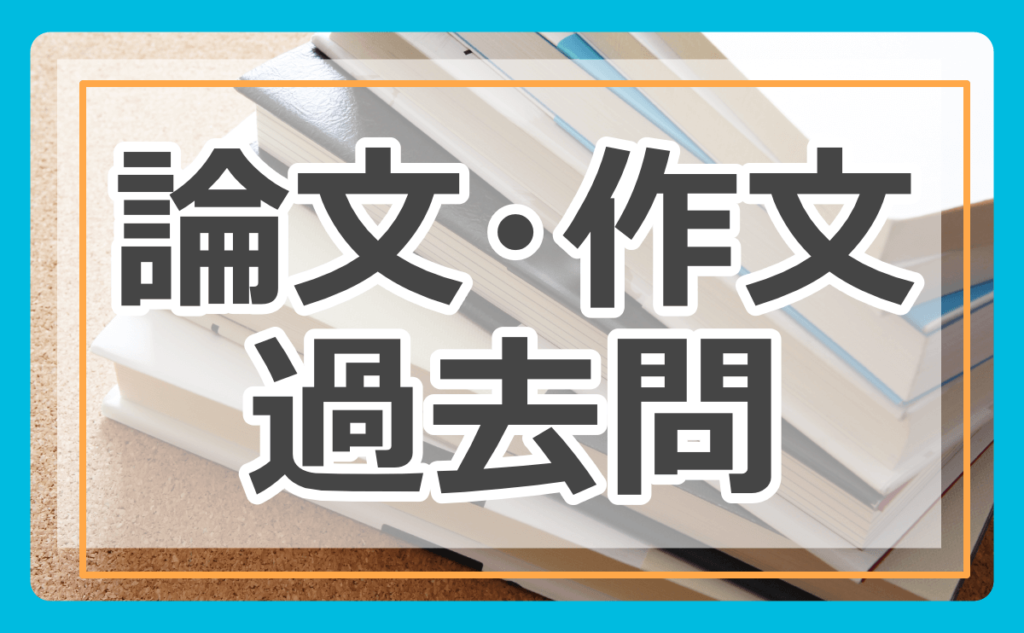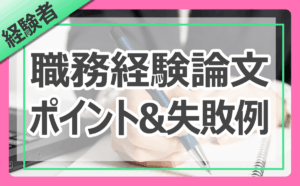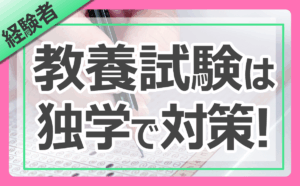【特別区経験者採用】課題式論文の傾向と対策をホンキで解説!
特別区経験者採用試験の受験を考えているみなさん、論文対策は進んでいますか?
特別区経験者採用の第1次試験では、教養試験のほかに「職務経験論文」と「課題式論文」という2つの論文試験が課されます。
この2つのうち、職務経験論文は比較的対策しやすいと言われるのに対し、課題式論文はどう対策したらよいか分からないという人が多いようです。
そこで本記事では、課題式論文に特化した対策方法を徹底解説します!
この記事で分かること
- 他の論文試験との違い
- 出題傾向
- 構成の立て方・書き方
ぜひ参考にしてください!
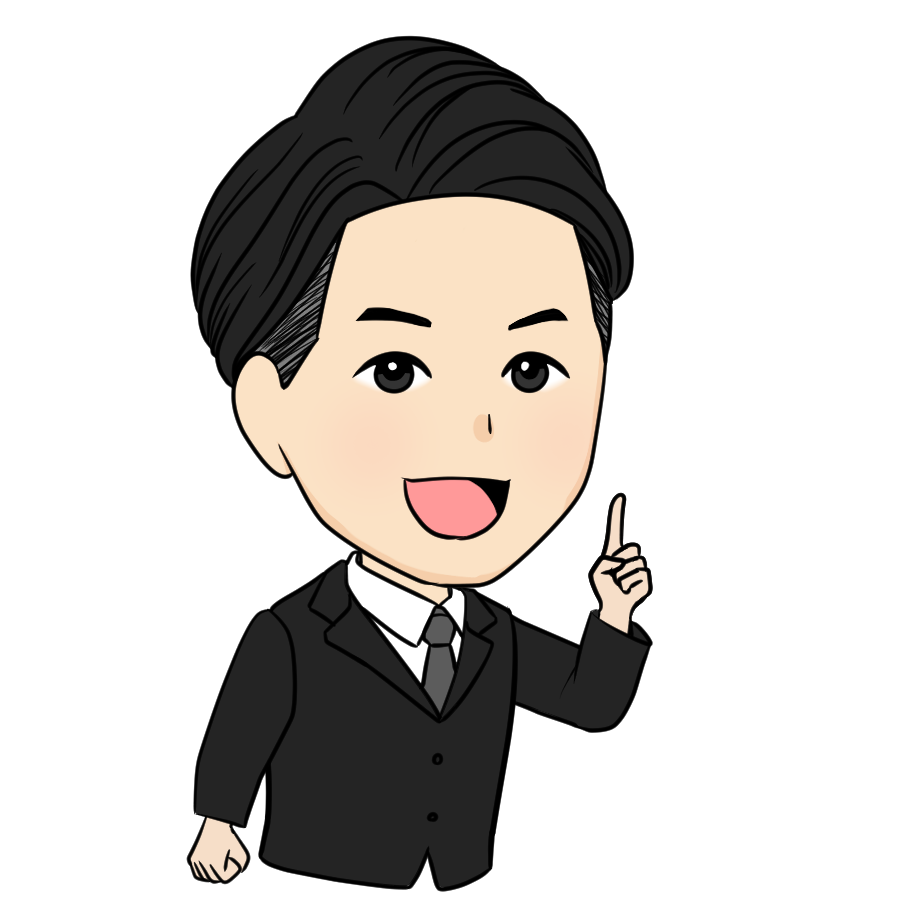
なお、特別区経験者採用の職務経験論文のポイントや注意点については、下記の関連記事で解説しているので併せてチェックしてみてください!
関連記事はこちら
課題式論文とは?
まず、職務経験論文とは特別区経験者採用の1次試験で実施される論文試験で、試験時間90分、文字数は1200~1500字です。
ここで過去問を確認してみましょう。
【2024年度】
①特別区の広報におけるSNSの利活用と課題について
出典:2024年度 特別区経験者採用試験 課題式論文問題
②業務におけるタイムパフォーマンス向上について
【2023年度】
①図書館機能の充実について
出典:2023年度 特別区経験者採用試験 課題式論文問題
②これからのイベント実施のあり方について
【2022年度】
①シティプロモーションについて
出典:2022年度 特別区経験者採用試験 課題式論文問題
②複雑化・多様化する区民ニーズへの対応について
このように2つの題が示され、どちらか1題を選んで書く形式となります。
こうして過去問を見てみると、難しそう…と感じる人が多いのではないでしょうか。
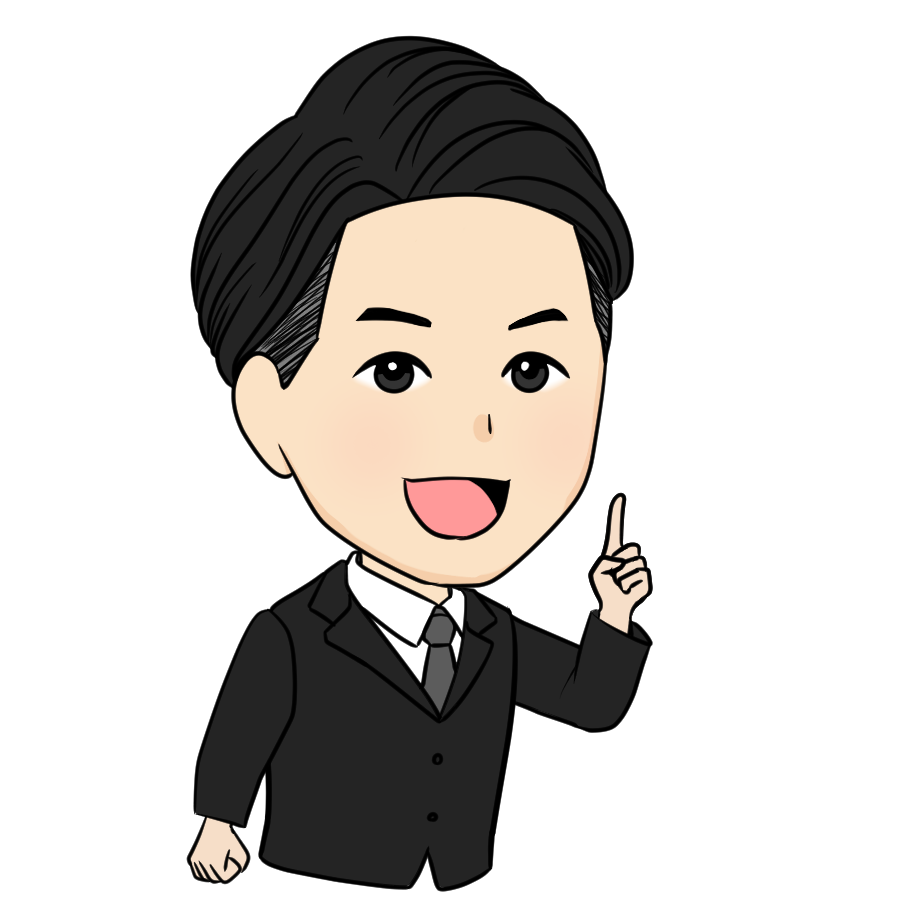
過去問の続きは下記の関連記事からチェックしてみてくださいね。
関連記事はこちら
Ⅰ類の論文試験との違い
主に大学生が受験する特別区Ⅰ類採用においても課題式論文が出題されますが、経験者採用とは出題傾向が異なる点に注意が必要です。
ここで出題傾向の違いを確認するために、Ⅰ類の論文問題を見てみましょう。
【2024年度】
①デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会のために、自治体におけるデジタル・トランスフォーメーション(DX)が推進されています。こうした中で、特別区においては、専門人材の体制整備やデジタルを活用した区民サービスの更なる向上などの課題が存在しています。このような状況を踏まえ、地方行政のデジタル化について、特別区の職員としてどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。
②我が国では、いじめ防止対策推進法の施行以降、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校での積極的な認知などによるいじめの早期発見・早期対応が進められてきましたが、不登校などの「重大事態」は増加し、深刻ないじめはあとを絶たない状況です。いじめといじめによる不登校の解消のために、関係機関と連携し、児童・生徒の声にもしっかりと耳を傾けながら必要な支援を行うことが重要です。このような状況を踏まえ、いじめといじめによる不登校対策について、特別区職員としてどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。
出典:2024年度 特別区Ⅰ類採用試験 論文問題
Ⅰ類と経験者採用の問題を比較すると、Ⅰ類のほうが出題文が長いことが分かりますね。
出題文が長いと大変そうに見えるかもしれませんが、むしろ課題についてある程度背景を解説してくれており、書く方向性も示されているため意外とそうでもないんです。
また、過去の出題テーマも「少子高齢化」や「地域防災」など、比較的分かりやすい行政課題から出題されています。
それに比べて、最初に示した経験者採用の課題式論文は、課題が短く示されているだけで他の背景情報が何もありません。
出題テーマもⅠ類とは異なり、社会人経験者として即戦力となる力を見るために「効率的な行政運営」や「行政における区民との協働」、「持続可能な財政運営」など、より踏み込んだ内容が出題されている点に違いがあります。
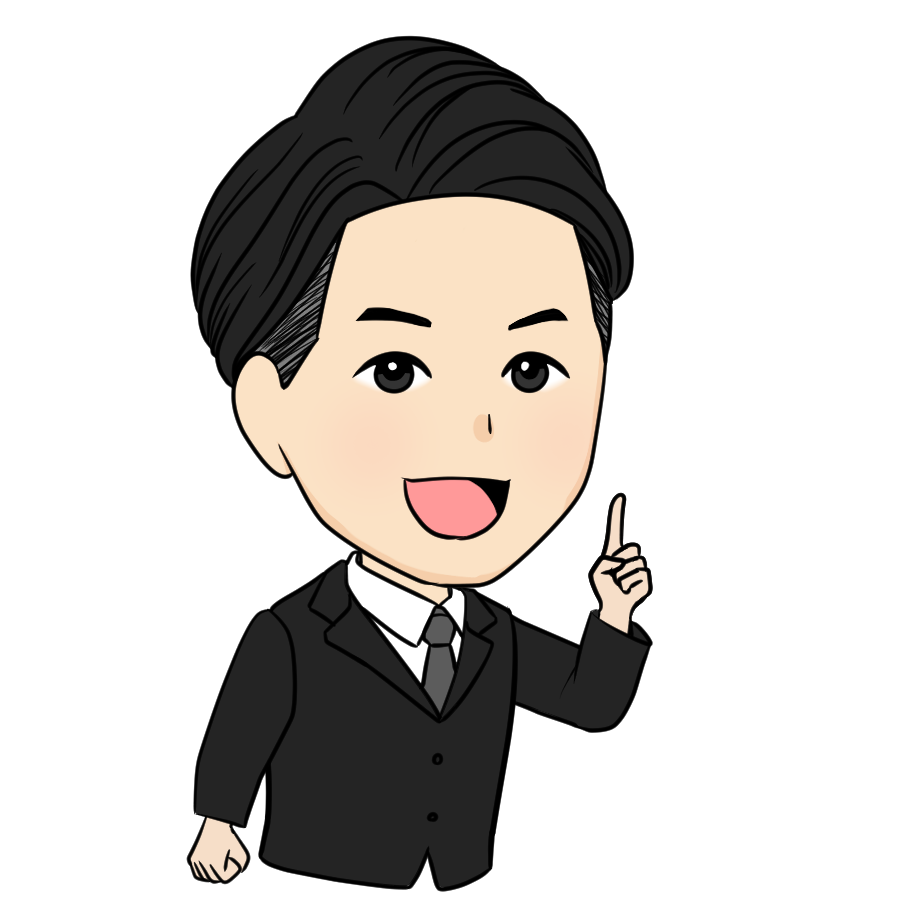
経験者採用は問題文が抽象的です。
論述の自由度が高いと言えばそうですが、どのような切り口でどう論じればよいかが分かりにくいことが難易度の高さにつながっています。
職務経験論文との違い
次に、経験者採用試験における2つ目の論文試験である「職務経験論文」とも比べてみましょう。
【2024年度】
行政におけるコンプライアンスの重要性について、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて採用区分における立場で論じてください。
出典:2024年度 特別区経験者採用試験 職務経験論文問題
職務経験論文においても課題式論文と同様に「〇〇について」というテーマがシンプルに与えられますが、これまでの職務経験と採用区分を踏まえて書くことになるため、文字数が稼ぎやすく、切り口や方向性も自然と定めやすくなります。
これと比較しても、課題式論文はテーマの背景から自分で論じなければならないため、より一層しっかりとした準備が必要なことがお分かりいただけると思います。
だからこそ、準備をした人とそうでない人の差が大きくつく試験であるとも言えるのです。
論文を書く前の下準備
ここからは、具体的な対策方法について解説していきます。
いきなり完璧な論文を書くことは難しいため、まずは下準備が必要です。
出題傾向を知る
経験者採用の課題式論文では、Ⅰ類よりも踏み込んだテーマが出題されるとお伝えしましたが、何が問われるかがさっぱり不明なわけではありません。
過去問をよく見てみると、似通ったテーマが繰り返し出題されていることが分かります。
この記事で分かること
- 「特別区の広報におけるSNSの利活用と課題について」(2024年度)
- 「これからのイベント実施のあり方について」(2023年度)
- 「複雑化・多様化する区民ニーズへの対応について」(2022年度)
- 「持続可能な財政運営と区民サービスについて」(2021年度)
- 「住民意識の多様化と自治体職員の役割について」(2020年度)
このように直近5年間に出題されたテーマを並べてみると、いかがでしょうか?
各年度ごとに表現は異なりますが、いずれも「多様化する住民に対する行政のあり方」に関わるテーマであることが分かると思います。
このように、経験者採用の課題式論文は過去問と類似するテーマが出題される可能性が高いため、まずは過去問を一通りチェックした上で徹底的に練習することが対策で最も大切なこととなります。
特別区の行政課題を知る
過去問を使って練習するといっても、出題テーマについての知識がなくては論文を書くことはできません。
まずは、特別区が現在抱えている行政課題とそれに対する施策をホームページなどで調べ、自分の意見をまとめておくことが大切です。
調べていくと、例えば「老朽インフラの更新」や「外国人住民との共生促進」、「住宅価格の高騰や空き家問題」、「脱炭素・環境政策の推進」など、様々な行政課題があることが分かると思います。
こうした各種課題について、特別区が現在どのような対策を取っているのか、そして今後どのように解決策を講じていくべきかを自分なりにまとめておく必要があります。
なお、特別区の課題や施策について調べる際には、ホームページ以外にも特別区職員研修所から毎年刊行されている『特別区職員ハンドブック』もオススメです。
特別区の組織や仕事が新人職員向けに分かりやすく網羅されているので、ぜひ手元において対策を進めましょう。
論文の構成と書き方のポイント
下準備ができたら、いよいよ実際に論文を書く段階に入ります。
ここでは、職務経験論文の基本構成とポイントについて解説していきます。
文章構成
本番でテーマを見てから構成を考えていたのでは、90分の制限時間内に書き終わらない恐れがあります。
そのため、課題式論文においては事前に「型」を確定させ、文章構成を決めておくことをオススメします。
オススメの構成は次のとおりです。
課題式論文の3段階構成
- 序論:出題テーマについて、背景や現状、今後の課題を示す(1段落)
- 本論:①で示した現状や課題を踏まえて、具体的な解決策を2~3つに分けてそれぞれ示す(2~3段落)
- まとめ:②の解決策に向けた特別区職員としての意欲を示す(1段落)
このように、大きく3つの内容に分けて4~5段落構成で書きましょう。
この構成に沿って書くことで、自分も書きやすく、採点者にとっても読みやすい論文になります。
決して流麗な美文である必要はないため、論理的で趣旨の明確な文章を作成することを意識しましょう。
また、文字数は1200字以上1,500字程度と指示されているため、書き始める前に段落ごとのおおよその文字数を割り振っておくと、あとになって「文字数が足りない!」ということもなく安心して書き進められます。
練習方法
課題式論文の練習をする際には、まずは過去問を可能な限りさかのぼり「知らない、分からない」というテーマをなくすことが大切です。
様々なテーマに触れておけば、本番で未知のテーマが出てきても焦らず対応できますし、既知のテーマを応用することもできるからですね。
そして各種テーマについてある程度理解が進んだら、実際に論文を書いてみましょう。
このとき時間を計りながら書きますが、練習し始めの頃は90分以内に書き終わらなくても構いません。
また、途中で書き進められなくなったら、参考書などを調べながら書いてもよいでしょう。
練習を重ねる中で、少しずつ自力で書けるように、そして時間配分を意識しながら時間内に収まるようにしていけばOKです。
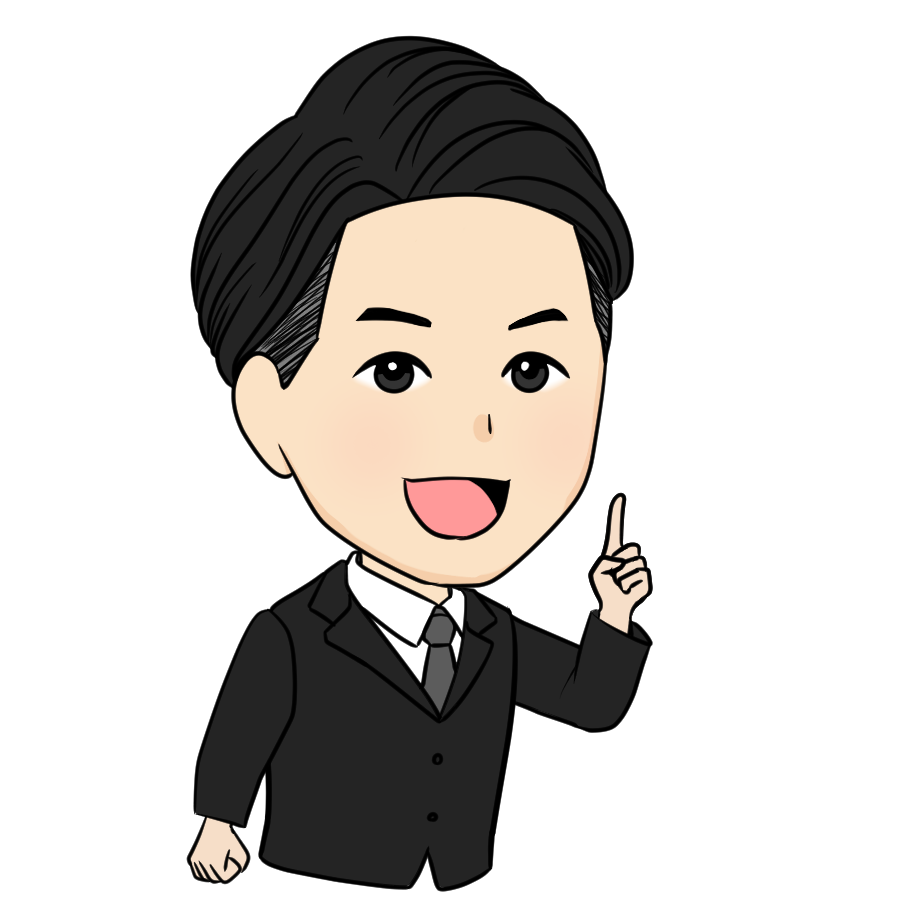
本番では完成した論文を見直しする時間も必要なため、制限時間より10分程度短い時間で書き上げられるようにしておくのがベストです。
練習する際の注意点
特別区の課題や施策について調べるのは大切ですが、調べてばかりでいつまでも実際に書かないのはNGです。
「参考書をすべて読み終わってから書く」というのでは効率が悪いため、課題等の調査と論文記述の練習は同時進行で行っていきましょう。
働きながら試験対策をしなければならない社会人にとっては効率も大切です。
ある程度の知識を頭に入れたら実際に書いてみて、書きながら疑問に思ったことをまた調べる、というやり方がオススメです。
ブラッシュアップする
論文というのは第三者に見てもらうことが必須の科目であり、自分では気づかない表現の曖昧さや不足している部分を指摘してもらうことが必要です。
自分以外の人からの客観的な意見を聞くことでより完成度の高い文章に仕上がるため、周囲の人や予備校講師などに読んでもらい、気づいた点をフィードバックしてもらってブラッシュアップを図りましょう。
まとめ
今回は、特別区経験者採用で課される課題式論文の対策について解説しました。
これからやるべきことは見えてきたでしょうか?
対策がしやすい教養試験や職務経験論文と比べて、課題式論文対策はつい後回しにしてしまいがちですが、そんな人が多いからこそ、ここをしっかりやった人が合格に近づきます。
ぜひ今日から、少しずつ対策に取り組んでいきましょう!
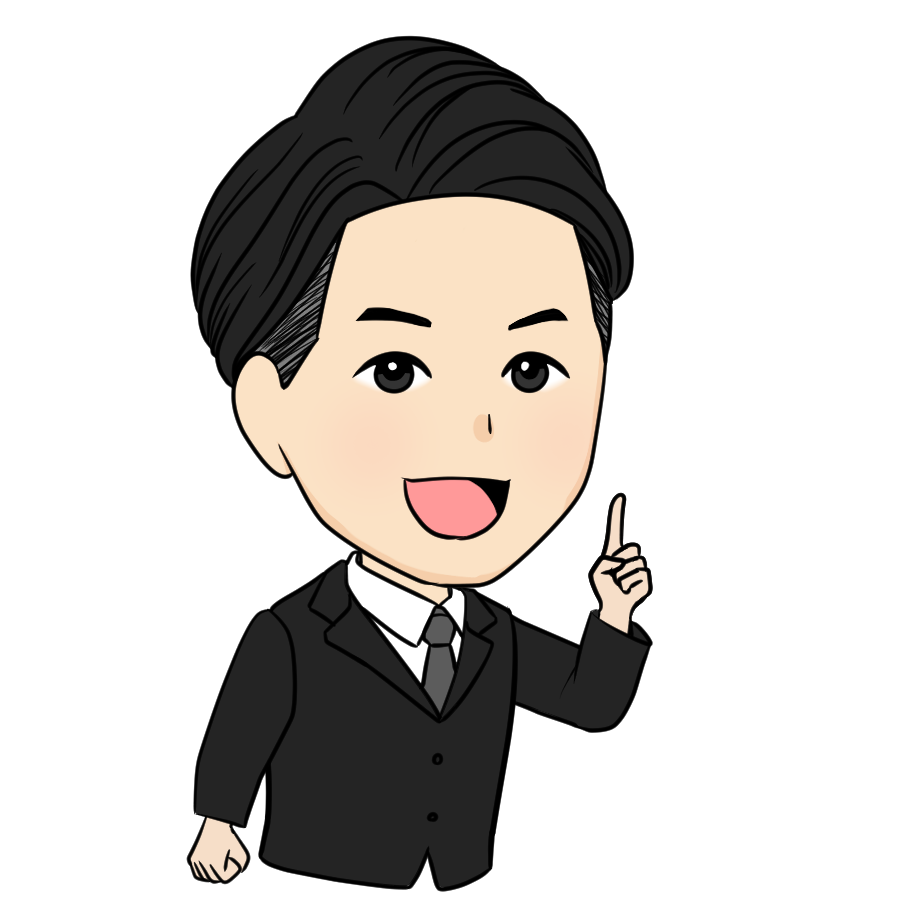
なお、特別区経験者採用の職務経験論文のポイントや注意点については、下記の関連記事で解説しているので併せてチェックしてみてください!
関連記事はこちら
予備校概要

- プロコネクトは「特別区対策に完全特化」した予備校です。コンセプトは「日本で一番特別区対策に強い予備校」&「必要な指導を、必要なときに必要なだけ」。個別ニーズに応じた指導を提供し、受験生の合格力を一気に高めます。特別区を目指すなら、専門予備校プロコネクト!
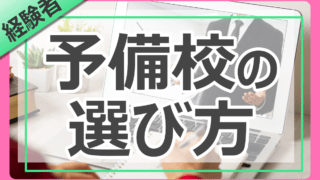 特別区経験者採用2025年12月22日【特別区経験者採用】社会人の予備校選び!おすすめの選び方とスクールは?
特別区経験者採用2025年12月22日【特別区経験者採用】社会人の予備校選び!おすすめの選び方とスクールは?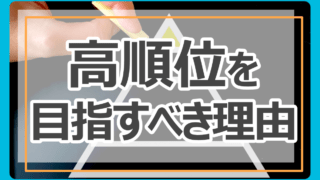 特別区全般2025年12月22日【特別区】高順位を目指すべき理由!低い順位は採用漏れ…?
特別区全般2025年12月22日【特別区】高順位を目指すべき理由!低い順位は採用漏れ…?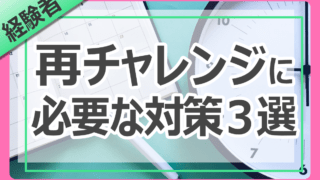 特別区経験者採用2025年12月22日【特別区経験者採用】再受験組が合格するための対策3選!
特別区経験者採用2025年12月22日【特別区経験者採用】再受験組が合格するための対策3選!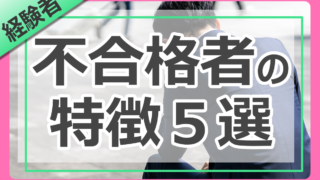 特別区経験者採用2025年12月22日【特別区経験者採用】不合格になる人の特徴5選!
特別区経験者採用2025年12月22日【特別区経験者採用】不合格になる人の特徴5選!